気まぐれ企画で打ち切りかと思われましたが…久方振りにやってきましたよ!
第3回となる塾用テキスト教材の紹介です。
前回は学書さんの「SPIRAL」、前々回はエデュケーショナルネットワークさんの「定期テスト対策 ワーク」と、大手有名出版社の紹介が続きました。
ここらで一発マイナー所を紹介するかと迷いましたが、こと自立学習用の教材に関して言えば、やはり安心・安定の大手出版社でしょ。
というわけで、今回ご紹介する塾用テキスト教材は…
「新ワーク」
作成・出版しているのは、学習塾や私立学校専用教材の開発・販売を行っている出版社「株式会社 好学出版」さんです。
例の如く、こちらで出版している教材の中には、私ゆうき塾長が愛用しているものも沢山あります。
高校受験生用の総復習教材「ウイニングフィニッシュ」や各種「入試完成シリーズ」、季節講習会用の短期テキスト「ウイニングサマー」に「冬の特訓ゼミ」等々。
そして、今日ご紹介する学校教科書に準拠した中学生用教材「新ワーク」に関しては、以前に執筆した塾用テキスト教材の説明記事でも少しだけ取り上げしました。

授業に使うメイン教材
としては理社ですが、
補助教材で英数国も
よく使ってますね。
ちなみに、この「新ワーク」と併せて使用できるICT教材に「映像 新ワーク」や「WEB BOOK」「TestMaker」等もありますが、別途有料サービスということもあり今回は割愛させていただきます。
それでは、以下で「新ワーク」の特徴について、前回までと同様に全体の特徴と教科別の特徴とに分けて一つずつ紹介していきましょう。
塾で使用するテキスト教材に悩んでいる方は、少しでも参考にしていただけたら幸いです。
「新ワーク」の特徴
では、まず「新ワーク」の中学生全学年版に共通する特徴5選を見ていきましょう。
これらの中には、前回・前々回記事で紹介した特徴と被っているものもありますので、そういった内容は一部省略してお伝えします。

選ぶ時の判断基準が同じ
だから、どうしても被る
のは仕方ないですね。
それでは、どうぞ↓
教科書準拠
教科書準拠の意味や特徴については、第1回の「定期テスト対策 ワーク」の紹介記事で説明していますので、疑問に思った方は是非ご一読ください。
学校の定期テストも考慮した授業をするのなら、やはり教科書準拠である方が便利ですね。
ちなみに、「新ワーク」が対応している教科書の出版社は以下の通りです。
【英語】東京書籍、光村図書出版、開隆堂出版、三省堂、教育出版、啓林館
【数学】東京書籍、教育出版、啓林館、学校図書株式会社、数研出版
【国語】東京書籍、光村図書出版、三省堂、教育出版
【理科】東京書籍、啓林館、学校図書株式会社
【社会】東京書籍、教育出版、株式会社帝国書院、日本文教出版

うん、主要な出版社は
大体おさえてますね。
特に英語と国語は教科書によって文章内容がガラッと変わる為、学校の定期テスト対策に重きを置く場合は注意しましょう。
その他の数学・理科・社会に関しては、上記の他に「標準版」もありますので、自塾の地域で採用されている出版社に対応していなくてもギリ何とかなります。
縮刷解答・解説
こちらも先述の教科書準拠と同様に、これまで紹介してきたテキスト教材にも見られた特徴です。
というか、教科書準拠のテキスト教材には縮刷解答・解説の場合が多いですね。

学校用ワークが同じ仕様
だからですかね。
いや、知らんけど。
更に、見やすいポイントがもう一つ。
前回ご紹介した「SPIRAL」もそうなんですが、問題文が黒色・解答が赤色の2色刷りになっているということ。
赤色の解答が目立つことで、問題・解答ともに黒色で記載されているものと比べて、丸付けの際に解答箇所を見つけ易いんですよ。
その他、英語・理科・社会の一部問題には縮刷部分と別に解説が書かれている為、その分だけ解説が詳しいのは良いですね。
「使いこなしガイド」で指導・学習の均質化
大体のテキスト教材には、はじめの1~2ページで申し訳程度に紙面構成や使い方の例が載っています。
この「新ワーク」も例外ではないんですが、ただ一味違う。
なんと、巻頭の4ページに渡って本書の構成や特長、学習の進め方などの活用方法が詳細に記載されているんです。
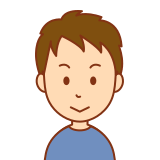
え…最初の説明って
そんなに重要か??

ぶっちゃけ
塾による
かな。
例えば、塾講師が板書するタイプの集団授業による一斉指導であれば、局所的な問題演習に使用するだけなので必要ないでしょう。
しかし、個別指導や自立型指導の場合は別です。
(指導形態の違いについては、以下の過去記事をご覧ください)
個別指導では、日によって担当講師が変わることは珍しくありません。
その際に、担当する講師によって授業の進め方が違っていたら、生徒が混乱してしまいます。
ですが、この「使いこなしガイド」を全ての講師が共有することで、指導オペレーションの均質化に役立つでしょう。

まぁ複数の講師を抱える
ような大規模な塾なら、
何かしらの対応は当然
考えてるでしょうけど。
また、自立型指導において生徒が学習の流れを忘れてしまった場合でも、講師に頼らずとも自ら確認することが出来ます。
どんな形態の塾でも便利に感じるようなものではありませんが、他のテキスト教材には見られない特徴なので、チェックしておいて損は無いですよ。
「徹底トレ」で基礎~標準問題の徹底復習
この新ワークには、本編の後に「高得点トレ!徹底トレ」というページが、本編の各単元・テーマに対応する構成で載っています。
単元・テーマ毎の暗記すべき内容やオーソドックスな問題、よく出る問題にフォーカスして、徹底的にトレーニングするページです。
教科毎の大まかな出題構成は以下の通り↓
【英語】新出単語、教科書本文の理解、基本文の文法問題
【数学】反復演習問題、重要語句や定義・定理・公式の穴埋め問題
【国語】漢字語句の読み書き、言語・文法の知識問題、問題演習
【理科】図表整理(穴埋め問題)、一問一答、問題演習
【社会】一問一答、単元のポイント(穴埋め問題)、問題演習
各単元・テーマで学んだ教科書内容について、基礎・基本を定着させることが目的の構成と難易度ですね。
自学に適した復習用ページなので、本編の単元学習が終わった後の復習として宿題で活用すれば、家庭学習の習慣化も期待できるかもしれません。

と言いつつ、僕の塾では
基本的に宿題を出さない
んですけどね。
ただ、僕の場合は授業の最初や最後の5~10分程度を使って、現状の理解度をチェックする機会は頻繁にあります。
そういった場面にも、この「徹底トレ」ページは重宝することでしょう。
無料搭載のWEBプリント作成サービス
塾用教材の出版社によっては、テキスト教材の他に自社で開発した各種ICT教材も提供しています。
この「新ワーク」を出版する好学出版さんも例外ではありません。
幾つかあるICT教材の中でも、僕が今回ご紹介するのは
WEBプリント作成サービス
自社教材や学校教科書に対応した問題プリントを簡単に作成することができ、テキスト教材だけでは物足りないと感じる学習塾には願ってもない、大助かりのサービスです。
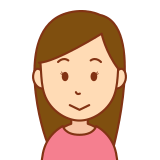
へぇ~~~。でも、
お高いんでしょう?

出版社によっては、
確かに有料の場合も
ありますね。
ところが、好学出版さんでは「新ワーク」など一部の対象教材を購入したら、なんと無料で利用できるんですよ。
(なので、「新ワーク」テキスト教材ではありませんが、付属サービスという体で特徴の一つとして挙げることにしました)
しかも、小難しい操作は一切必要なくて、専用サイトに入ったら以下のステップで作成から印刷までスイスイ出来ちゃいます。
①出題範囲の設定
教科書ページの範囲を指定、または単元名を選ぶだけ。
②問題量の設定
ページ数、または問題数を指定するだけ。
③出題形式の設定
教科によって、以下の中から複数選択可能。
【英語】新出単語、選択、穴埋め、並べかえ、書きかえ、英作文、読解(教科書本文)、読解(教科書本文以外)、その他
【数学】計算、大問形式、作図、記述、用語
【国語】漢字、知識、読解、初見の文章
【理科/社会】一問一答・大問形式・図表整理
※ただし、単元によっては該当の出題形式が無い場合もあります。

英語の自由度が
異常に高い…。
④レベルの設定
基本・標準・応用の3段階から複数選択可能。
※ただし、単元によっては該当のレベルが無い場合もあります。
⑤タイトルの設定および学年・クラス・名前欄・問題数・2ページ目以降のヘッドに関する表示・非表示の設定
お好みでどうぞって感じですね。
⑥出題する問題や順番の設定
ドラッグ操作またはボタン一つで、出題する問題の入れ替えや、出題する順番の並び替えが可能。
⑦PDF形式で出力・印刷
PDFファイルとしてパソコンに保存することも可能。
(何パターンか作成して貯めておくことや、時間をおいて印刷することも出来ますよ)

7ステップありますが、
説明書やガイドは全く
必要なく、ほぼ直感的
な操作で大丈夫です。
「この問題は良いけど、この問題は要らないなぁ…」
そんな、プリント教材を扱っていると必ず直面する悩みも、このWEBプリント作成サービスなら余裕で解決します。
定期テスト範囲や授業の進度にピッタリ合った問題プリントを手軽に作成できるので、新ワークを主軸としたサブ教材として、このサービスは大いに役立つでしょう。
「新ワーク」教科毎の特徴
さて、続いては株式会社好学出版さんの「新ワーク」教材について、教科毎の特徴を見ていきましょう。
「新ワーク」は通年教材で、中学1・2・3年生それぞれ主要5教科(英語・数学・国語・理科・社会)全て揃っています。
※社会は地理Ⅰ・Ⅱと歴史Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、そして公民の計6冊に分かれており、学年や時期によって要不要が異なりますので注意して下さい。

社会は 地域や学校で
地理・歴史の進め方
が異なるから、大抵
分冊になりますね。
これまで紹介してきた2社のテキスト教材とは似ているようで一味違いますので、この先の内容も必見です。
それでは、どうぞ↓
新ワーク(英語)の特徴
好学出版の「新ワーク」英語テキスト教材の特徴は、大きく以下の2点です↓
①各単元の学習内容に対応したリスニング演習ページで聴く力UP!
②オリジナルの長文読解と自由英作文で各単元のテスト対策が可能。
英語テキストの構成は、各単元のパート毎に
・基本文の解説
(基本文による文法事項の説明)
↓
・基本文の問題
(基本文に関する文法問題)
↓
・新出単語
(新出単語の意味&スペル問題)
↓
・重要表現
(重要表現に関する問題)
↓
・教科書本文の理解
(教科書本文の読解問題)
↓
・英作文&表現力
(和文英訳などの英作文問題)
という流れで、各単元の後半には
・練習問題〈基本文〉
(基本文の文法問題まとめ)
・練習問題〈教科書内容の確認〉
(単語・重要表現の問題まとめ)
・定期テスト予想問題〈必修〉
および定期テスト予想問題〈完成〉
(単元の総まとめ問題)
・リスニング
(単元のリスニング問題)
・文法トレーニング
(単元の文法問題まとめ)
加えて巻末には
・基本文総チェック
・不規則動詞の変化表
という流れで、各単元の新出単語から重要表現、文法事項まで学習できる構成です。

パート別の問題ページ
の項目が多いですけど、
各パート見開き1ページ
にまとまっています。
英語テキスト教材の特徴1つ目は、各単元の学習内容に対応したリスニング演習ページがあるということ。
大学入試と同様に、高校入試や中学校の定期テストにおいてもリスニング問題の重要性は徐々に高まっています。
しかし、特に教科書準拠のテキストだとリスニング問題が無かったり、あっても申し訳程度といった場合も少なくありません。
ですが、この「新ワーク」では単元毎に丸々1ページ割いてリスニング問題が掲載されています。
構成はシンプルで、新出単語・基本文・重要表現のディクテーションから、イラストを使った問題や適する英文を選ぶという2ステップ形式。
集団指導はともかく、個別指導や自立型指導となると、塾の授業でリスニング問題の演習を行える機会は決して多くないでしょう。
定期テスト範囲の区切りとなりやすい単元毎に、リスニング問題の対策を行うページが設けられているのは嬉しいですね。

音源の再生は、集団指導
ならPCから、個別指導
などではタブレット端末
+イヤホンが無難かな。
さて、続いてもう一つの英語テキスト教材の特徴は、オリジナルの長文読解と自由英作文があるということ。
各単元の終盤にある「定期テスト予想問題〈完成〉」ページは、教科書に無いオリジナル長文の読解問題が出題されている、実力テスト型の定期テスト予想問題です。
当該単元までの既習の語句・文法事項も含めた内容となっており、知識・技能・思考力の分類別に100 点満点の配点付きで、実力テストを意識した総合的な力が試される問題に取り組めます。
教科書準拠のテキスト教材では、教科書本文の一部抜粋で読解問題を出題する場合が殆どの中、このように初見の英文を読解する練習が出来るのは嬉しいですね。

読解用テキストも色々
ありますが、受験生向け
で1・2年生には難しい
ものが多いんですよ。
新ワーク(数学)の特徴
好学出版の「新ワーク」数学テキスト教材の特徴は、大きく以下の2点です↓
①教科書+アルファの細かいテーマ設定による例題・類題。
②既習内容の復習から始まるスムーズな単元学習。
数学テキストの構成は、各章における各単元の最初に
・復習
(関連する既習内容の復習問題)
その後、テーマ毎に
・例題
(用語などのポイント解説と例題・解き方)
↓
・類題
(例題の類題による確認問題)
↓
・練習問題A
(標準レベルの練習問題)
↓
・練習問題B
(少し難易度の高い応用問題)
また、各章の最後には追加で
・定期テスト予想問題〈必修〉
および定期テスト予想問題〈完成〉
(章の総まとめ問題)
また、章によっては更に追加で
・トレーニング
(特に重要なテーマの基礎レベル問題)
という構成になっています。
さらに、巻頭部分には前学年(1年生テキストには小学校内容)の復習問題が、見開き1ページ用意されています。

スッキリした構成で
指導しやすいですね。
例題・解説からの類題、練習問題へと進んでいく流れは、数学テキストのテンプレにして王道。
「新ワーク」では、教科書の代表的な問題をテーマとして細分化することで、教科書内容の理解と反復演習による解き方の定着に重きが置かれています。
じゃあ、教科書レベルの基礎的な問題しかないのかというと、全然そんなことはありません。
定期テストによく出る例題の応用パターン問題については、教科書に掲載されていなくても「プラスα」テーマとして取り上げられている為、これ一冊でバッチリ応用力も鍛えられるでしょう。
このように基本から発展内容まで細かく分けられたテーマを、例題をもとに一つずつ理解を進めていけば、確実に数学の力がついていく筈です。

定期テストで平均点以下
の生徒には、やや難しい
かもしれませんけど。
テーマの細分化と合わせて、スムーズに学習を進める工夫がもう一つ。
それは、主要な単元の最初に、当該単元の学習内容に関連した既習事項の復習と確認問題が掲載されているということ。
“数学は積み上げ型の教科”という言葉は、多くの人が一度は耳にしたことがあるでしょう。
そう言われるのも納得で、確かに数学で何か分からない事がある場合には、実のところ現行単元よりも遥か前の学習内容が曖昧になっていることが殆どです。
であればこそ、新しい単元の学習を始める際には、はじめに関連事項の理解度を把握しておくことは必須。
この復習が要所に設けられていることで、いざ新たな学習を始める前に簡易的なチェックが出来ます。

本人も自覚が無く
“意外と忘れてる”
ってことも多い
ですからね。
新ワーク(国語)の特徴
好学出版の「新ワーク」国語テキスト教材の特徴は、大きく以下の2点です↓
①各題材に合わせた豊富な読解問題で演習量UP!
②巻末収録の聞き取り問題ページで定期テスト対策。
国語テキストの構成は、詩歌・古典や言語事項の単元はじめに
・知識のまとめ
(重要知識の説明)
その後、読解単元(現代文および詩歌・古典)では
・読解問題
(場面の区切り毎の読解問題)
↓
・定期テスト予想問題
(解答欄が独立したテスト形式問題)
↓
・ヒミツの暗記ノート
(単元の要点確認問題)
また、言語事項の単元では
・演習問題
(言語事項に関する練習問題)
さらに、巻末には特集として
・聞き取り問題
(各種テーマの聞き取り問題)
以上のような流れになっています。

特に 読解単元の
問題量の多さが
際立ってるかな。
そう、各単元の読解問題は題材文の長さに応じた回数が用意されており、その後の定期テスト予想問題も1~2回分が掲載されています。
また、徹底トレには各単元に対応した漢字および知識の確認と、読解問題の各回に対応した読解問題を収録。
出版社による定期テスト分析をもとに、よく出る場面を区切り良く掲載しているので、文章の展開を的確に押さえられるでしょう。
出題形式に関しては、全国的な記述問題の増加の対策として、時に40字超えの記述問題も。
本編の全ての記述問題について、内容・形式が確認できる採点基準が設けられているので、丸付け直しをする際も安心です。

国語の記述問題の採点
が苦手っていうのは、
きっと僕だけじゃない
ハズ……っ!
もう一つ、この「新ワーク」国語テキスト教材の特徴として際立っているのは、巻末に収録されている聞き取り問題の特集ページです。
定期テストでの出題も増えている聞き取り問題が、各学年5ページ分掲載されています。
説明文・話し合い・スピーチ・インタビュー等、国語の聞き取り問題で見られる様々なジャンルからの出題で、各学校の出題傾向に合わせた対策が可能。
タブレットやスマホで二次元コードを読み取って再生できる他、解答・解説には音声の台本付きで、自学用として活用するのも良いでしょう。
ちなみに、各ページの下半分はメモ欄になっていて、実際のテストのようにメモを取りながら音声を聞く練習が出来ます。

聞きながらメモを取る
スキルは、英語のリス
ニングにおいても重要
ですよね。
新ワーク(理科)の特徴
好学出版の「新ワーク」理科テキスト教材の特徴は、大きく以下の2点です↓
①フルカラーで重要事項を1ページにまとめた「要点のまとめ」。
②「トレーニング」ページで頻出の計算・作図問題を反復演習。
理科テキストの構成は、各分野の単元毎に
・要点のまとめ
(単元における重要事項の説明)
↓
・確認問題
(一問一答と重要語句の記述)
↓
・練習問題
(練習問題と入試レベルの”差がつく1題”)
また、単元によっては「トレーニング」という特集コーナーが練習問題の後に挿入されています。
加えて、各分野の最後には
・定期テスト予想問題〈必修〉
および定期テスト予想問題〈完成〉
更に、巻頭部分には前学年の物理・地学分野(1年生テキストには小学校内容)それぞれの「定期テスト予想問題〈必修〉」と「定期テスト予想問題〈完成〉」も掲載されており、復習を兼ねた腕試しに打ってつけです。

巻末の徹底トレを
含めると問題量も
丁度イイ感じかな。
この「新ワーク」理科テキスト教材の最大の特徴は、ズバリ簡潔に説明された「要点のまとめ」に他なりません。
「要点のまとめ」とは、各単元における教科書の重要事項について、色鮮やかなフルカラーで図表を交えキッチリ1ページにまとめられた単元の導入ページです。
(理科は色の違いに着目する内容が幾つもありますので、フルカラーによって視覚的な情報の質が高まり、より記憶に残りやすくなる効果が期待できますね)
特に理科で重要となる実験や観察に関しては、教科書で扱われている実験のポイントとなる目的・手順が、結果や考察と合わせてスッキリ整理されています。
普段の予習・復習における単元学習は勿論、定期テスト前の最終チェックにも役立つでしょう。

自分でノートまとめ
してもいいんだけど、
なにぶん時間と手間が
かかりますからねぇ。
もう一つの特徴は、丁度良い塩梅で適所に設けられた「トレーニング」です。
「トレーニング」とは、定期テストで頻出の基本的な作図・計算・実験・観察問題を集中的に取り組むページです。
例題と類題で構成されており、定期テストで確実に正答する為の練習を重ねることで、本番での得点力アップが期待できます。
また、当該ジャンルの問題を苦手とする生徒に対しては、メインの学習を終えた後の演習用課題とするのも良いでしょう。
作図・計算・実験・観察に特化した専用のテキスト教材もありますが、難易度にバラつきがあって気軽に使うのは難しい場面も少なくありません。
ちょっと追加で問題を解きたいという状況において、単元学習に沿った自然な流れで取り組めるので、スムーズに理解を深めることができますよ。

理科の計算が苦手な子
って多いですからねぇ。
新ワーク(社会)の特徴
好学出版の「新ワーク」社会テキスト教材の特徴は、大きく以下の2点です↓
①一問一答と資料の図表整理で知識事項を確実に定着。
②豊富な資料読み取り問題と記述問題で応用力が鍛えられる。
他教科のテキストが学年別の計3冊に対して、前述の通り社会テキストは地理Ⅰ・Ⅱと歴史Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、そして公民の計6冊です。
(概ね中1が地理Ⅰと歴史Ⅰ、中2が地理Ⅱと歴史Ⅱ、中3が歴史Ⅲと公民に該当します)
いずれの冊子も構成は同じで、各章の単元毎に
・要点のまとめ
(単元における重要事項の説明)
↓
・確認問題
(重要語句の一問一答)
↓
・練習問題
(図表の穴埋めと大問形式の問題)
↓
・定期テスト予想問題〈必修〉
(単元の総合問題)
そして、各章の最後には追加で
・定期テスト予想問題〈完成〉
(複数単元の総まとめ問題)
という流れで、各単元の重要語句や関連事項について、色んな出題形式で学習できる構成です。

要点のまとめは箇条書き
で整理されているので、
細かい内容を知るのには
少し不向きかな。
ただ、重要事項を確実に押さえて記憶に定着させる為の段階的な一連のステップには、一切の無駄がありません。
確認問題では、要点のまとめで学んだ定期テストにおける頻出の重要用語について、覚えているかどうか一問一答形式の問題でファースト確認。
続く練習問題は二段構成で、左ページ「地図や資料でまとめよう」では図表の穴埋め問題を通して、単元の重要事項を視覚的に整理しながらセカンド確認。
右ページ「問題を解いてみよう」では、基本的な知識事項を大問形式で出題することで、より実践的な形で理解を深めるサード確認。
色んな出題形式で多角的に重要語句を問うことによって、テストにおける得点力アップに繋がる学習が期待できるでしょう。

よく見る社会テキスト
のポピュラーな構成で
すけど、それだけに
安定感がありますね。
以上の問題は基本レベルですが、ここから先は難易度が上がります。
「定期テスト予想問題〈必修〉」の方は、当該単元の内容だけで構成されており、前述の練習問題に続く教科書知識の更なる理解・定着を図るページです。
実際の定期テストのような独立した解答欄と100点満点の配点付きで、よりテスト本番を意識した形式の予想問題となっています。
一方で「定期テスト予想問題〈完成〉」の方は、複数の単元を範囲とした実力テスト型予想問題で、より幅広い知識と応用力が求められるでしょう。
両者に共通するのは、地図・資料の読解問題や記述問題が多く掲載されているという点。
テキスト教材によっては、資料の読解だけ・記述問題だけの特集ページを設けている場合もあり、それはそれで集中的に練習したい時は非常に便利です。
ただ、その場合は問題形式が限られていることから、どうしても一つ一つの問題に繋がりが無くなってしまいます。
あくまで大問中の設問として、かつハイレベルな資料読解や記述問題を多めに解きたいというのなら、この「新ワーク」が有力な候補となるでしょう。

資料の読解や記述問題
が多い点は近年の入試
傾向を押さえていて、
流石は教材会社ですね。
最後に
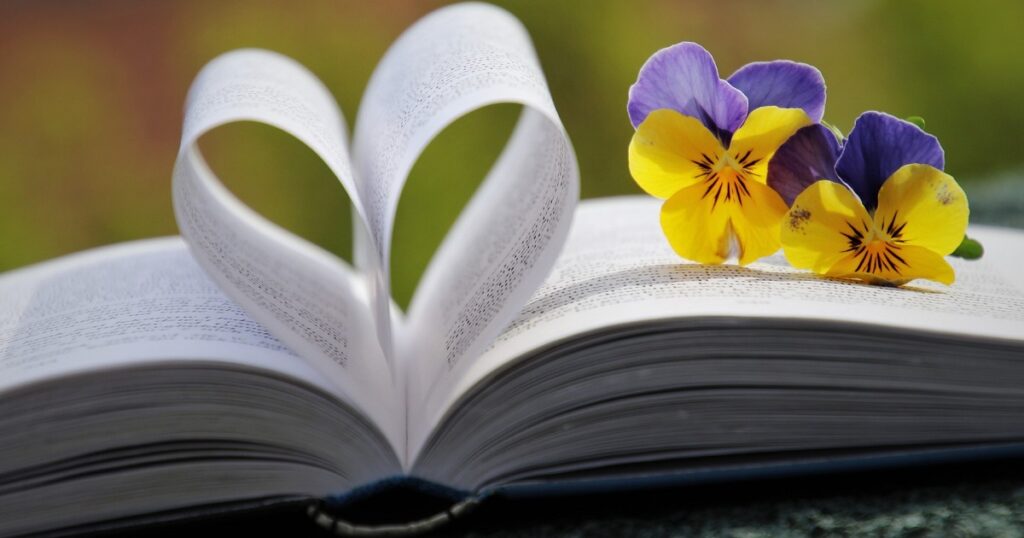
というわけで、いかがでしたか?
好学出版さんの「新ワーク」テキスト教材は、中学生の成績中・上位層を中心に僕の塾でも授業のメインまたはサブテキストとして愛用しています。
教科によって予習向き・復習や演習向きと印象が異なりますので、教科毎に使い分けるのがオススメです。
こと学校の定期テストに関して言えば、このテキストを完璧にしておけば概ね満点を狙えるでしょう。

平均点未満の成績下位層
には少し厳しいかもしれ
ませんが、まぁその辺は
個々の生徒次第ですね。
以上のことを踏まえて、もし好学出版さんのテキスト教材にご興味を持った方は、まずは実際に中身を見てみるのがオススメです。
公式ホームページには「新ワーク」についてページ毎の特徴が説明されていますし、多くのテキスト教材はPDFで見本サンプルを見ることも出来ます。
好学出版のホームページから直接注文・購入は出来ませんが、例えば以下の学習塾用教材の販売会社サイトから購入できますので、気になる方は是非チェックしてみて下さい。

僕は塾まるごとネット
の方を利用しています
けど、その辺は好み
ですかね。
当記事の内容が、これから学習塾経営を始める予定の方・まだ経験が浅い方にとって、少しでもお役に立てたら幸いです。
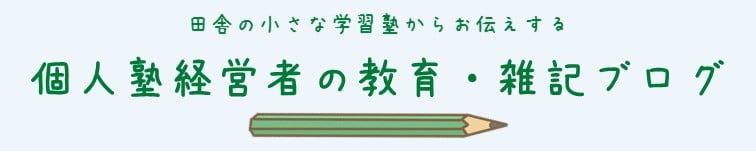




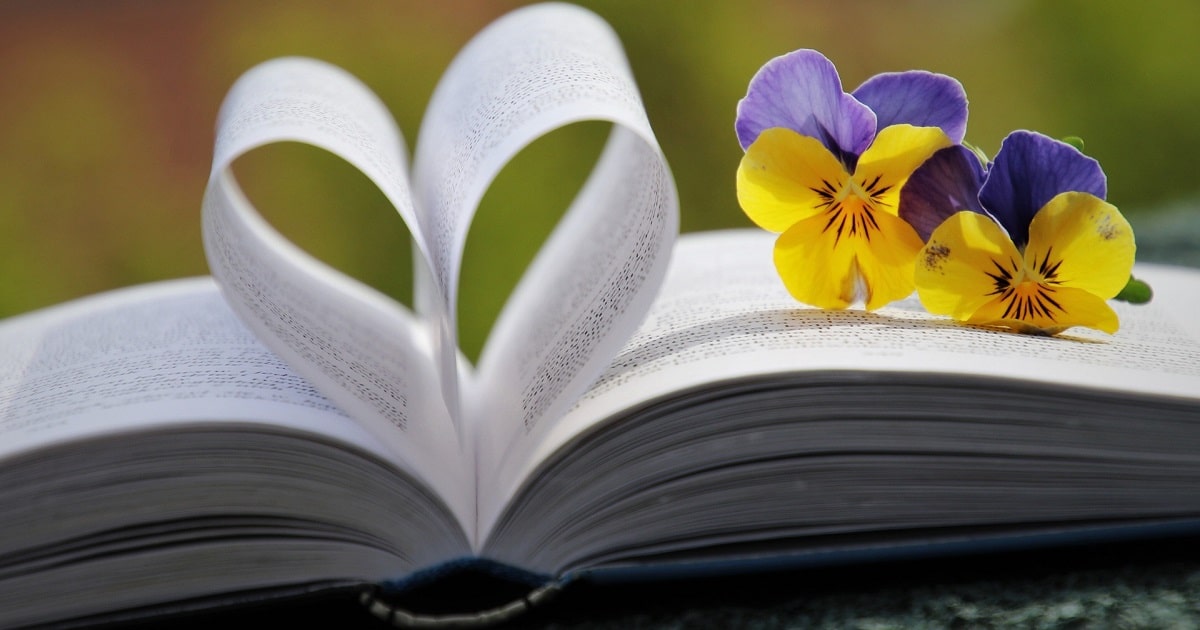


コメント